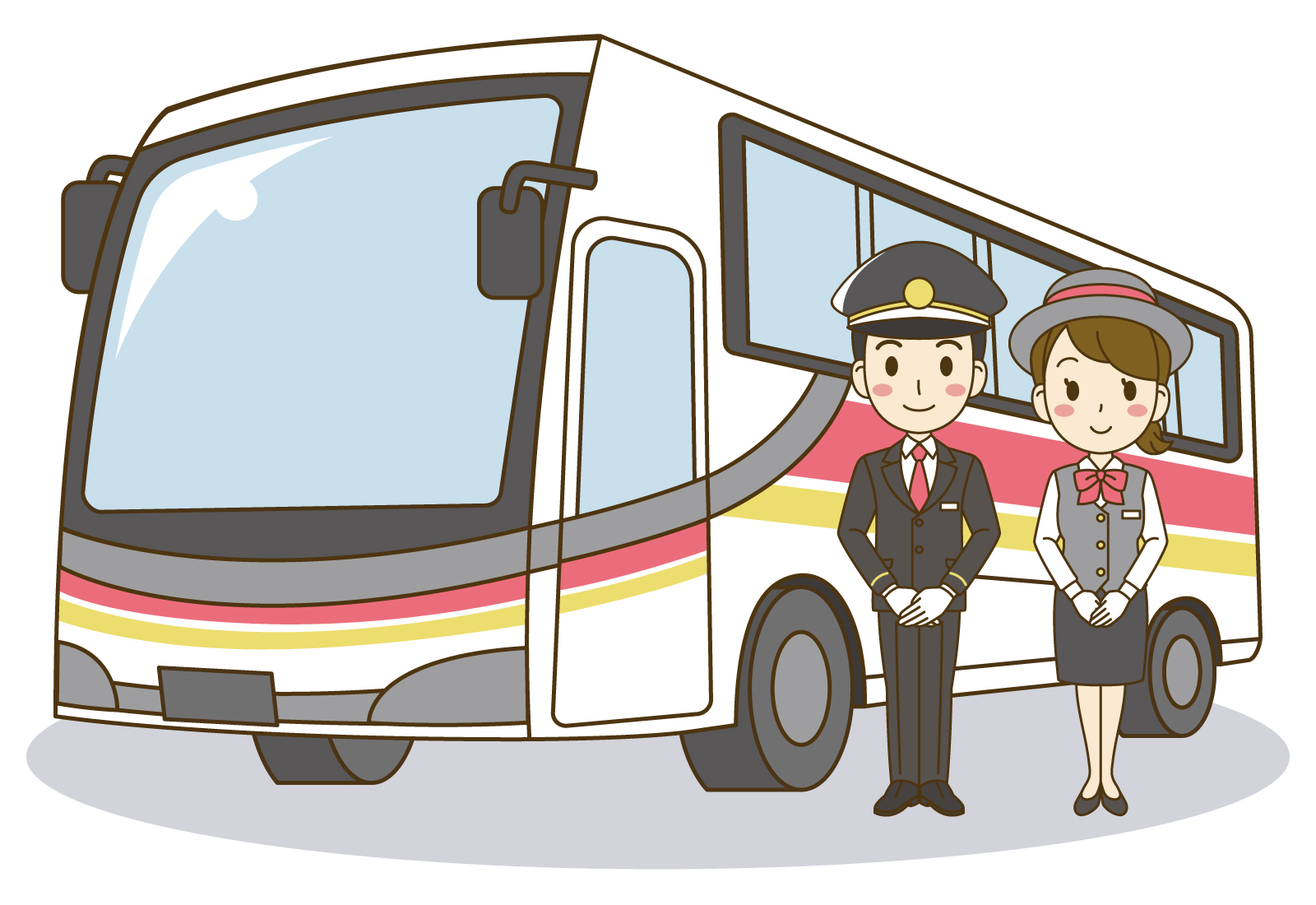伝統工芸に触れよう〜沖縄の伝統美・琉球びんがた〜

こんばんは!Runa旅です。
かつては琉球王朝の王族や氏族が身につけた格式高い染め物でございます。現在ではファッションや小物雑貨にも取り入れられ沖縄のお土産としても人気を集めています。今回はそんな沖縄の伝統工芸品・琉球びんがたの魅力をお伝えいたします。
琉球びんがたとは?
まずはじめに、びんがた(紅型)は沖縄の自然の中から生まれ独自の染技で育まれた沖縄染物の総称になります。13世紀ごろから始まったとされており、14〜15世紀に発展したと伝えられております。
かつて琉球王朝では近隣諸国との交易が盛んに行われておりました。インド更紗、ジャワ更紗なども交易品として多く運ばれてきました。そこから沖縄独自の風土に日本的な優美さやさまざまな国の技法を織り交ぜ発展してまいりました。
その後は琉球王朝の保護のもと礼装や神事の装束として重宝されてまいりました。
(“びん”は色彩を“がた”は模様の意と解釈する見方がございます)
琉球びんがたの種類
紅型
さまざまな手法を取り入れ、白地紅型、染地紅型、返し型や手附紅等に染め分けられます。これはカタチキと呼ばれる糊置防染手法による型染めになります。型紙を当て、生地に糊を塗りその後取り去った型紙に模様の部分に色を刺すといった染め方になります。
藍型(イェーガタ)
藍の濃淡や墨で染められたびんがたを藍型と申します。型紙は染地(線彫り)型を使用します。藍の色の変化と地の白で大きめの模様を表現いたします。
どちらかといえば、夏の衣料に好まれてまいりました。
筒描き
糊引(ヌイビチ)と呼ばれる技法が用いられる筒描きは型紙を使用いたしません。防染糊を糊袋に入れ、糊を絞り出しながら生地に模様を書き出していきます。その後、模様の部分に色を差す技法になります。大変難しい技法になり、かなりの時間もかかってまいります。
婚礼などの祝義の際の風呂敷や豊穣祭などに使用される大きな舞台幕などに使用されております。
琉球びんがたを体験してみよう!
魅力たっぷりの琉球びんがた。お土産にしたい!と思っていただいている方も多いかと思います。実は自分の好みのびんがた染めを体験することができ流工房がございます。初心者の方から気軽に楽しめるハンカチからTシャツやバックまで工房によって体験内容が違います。是非お好みの工房へ出かけてみてくださいね。
城紅型染工房
こちらの工房さんは伝統を大切に守りながら新しい感覚をプラスして日々の生活に彩りを添えるようなびんがたアイテムを作られております。
タペストリーやトートバック、コースター染め体験が用意されております。スタッフさんもサポートしてくださいますので安心して体験することができます。4歳のお子様から体験いただけますので家族旅行の思い出にも最適ですね。
琉球びんがた工房 ちゅらり
ちゅらりさんでは沖縄の豊かな自然・文化・琉球紅型古典紋様に日々の暮らしで感じたことをプラスして今の沖縄らしさを表現された紅型を見ることができます。
楽しく学びながらびんがたの魅力を深めていく教室が開講されております。継続的に学ぶ教室と単発で学べる教室が開講されております。継続的に学びたい方も気軽に体験したい方にもおすすめの工房さんです。
沖縄伝統工芸・琉球びんがたは知れば知るほど沖縄の文化や歴史の詰まったものでしたね。ぜひ沖縄に行かれた際にはお気に入りの琉球びんがたのアイテムを手にしてみてくださいね。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。