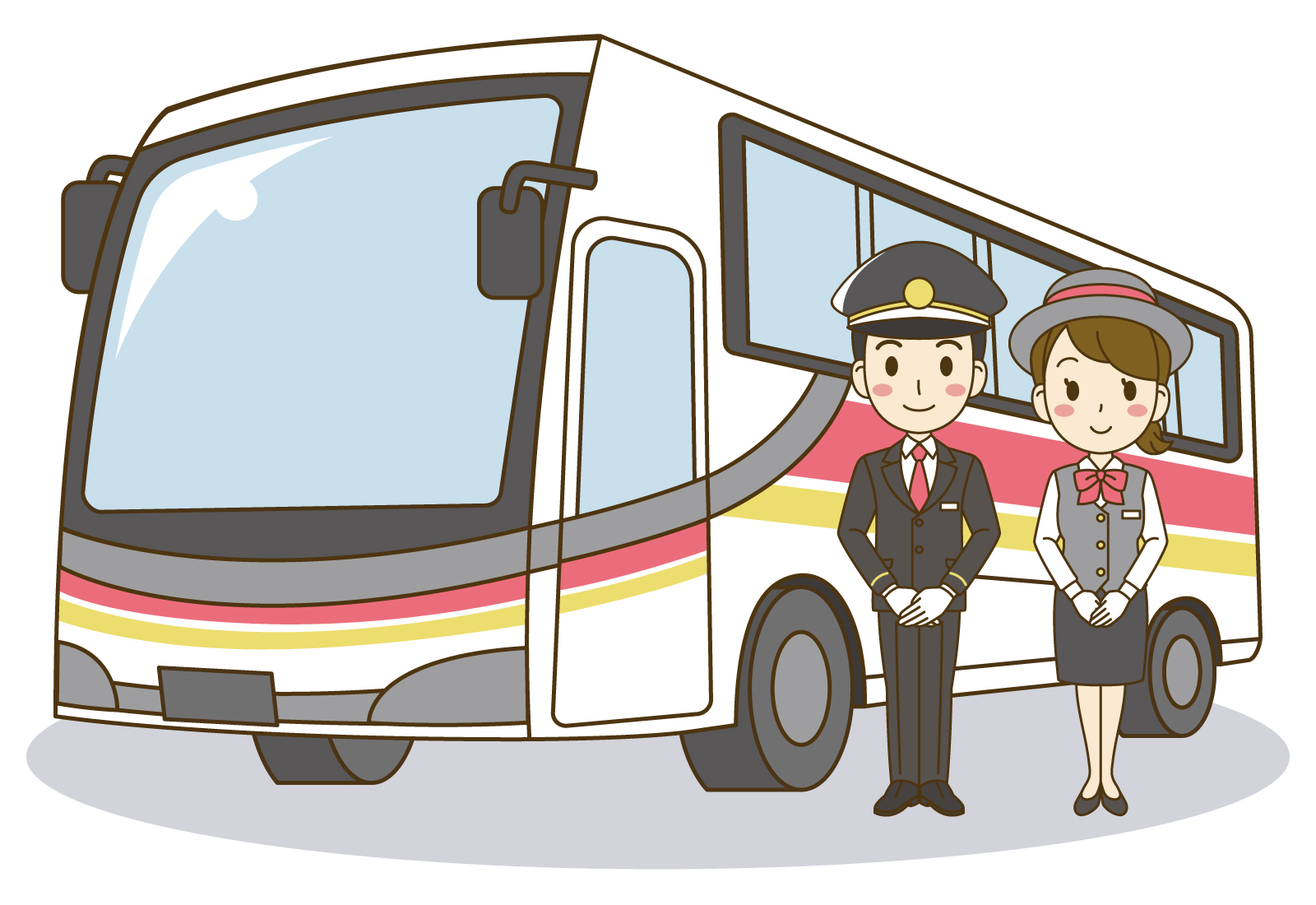【秋の旅】お月見と彼岸花巡り〜秋を感じるおすすめ観光

こんにちは!Runa旅です。
夏の暑さも少しづつ落ち着き、秋の気配も感じられる9月。そこで本日は、日本の秋を代表する風物詩“お月見(十五夜)”と彼岸花をテーマに、その歴史や文化を交えながらご案内してまいります。
秋の行事・お月見(十五夜)の歴史と文化
お月見は“中秋の名月”を鑑賞する日本の伝統行事でございます。
そのルーツは中国にあり、唐代の宮廷では月を愛でる宴“観月”が盛んに行われておりました。そして、平安時代に伝わり、貴族たちは舟遊びをしながら月を眺めました。和歌を詠み、音楽を奏でたと言われております。
その後、庶民にも広がり、農作物の収穫と結びついていきました。十五夜は稲作の節目でもあり、月に感謝し豊作を祈る日でもあったのでございます。
特に里芋を供えることから「芋名月」と呼ばれることもあります。
お月見の文化的意味
月見団子:丸い形は満月を象徴し、子孫繁栄や結びつきの意味が込められています。
ススキ:魔除けとしての役割があり、稲穂に似ていることから五穀豊穣の象徴とされます。
月と文学:『源氏物語』や『枕草子』にも、月を眺める情景がたびたび描かれています。
2025年の中秋の名月は?
2025年の 中秋の名月は9月6日(土)。
今年はぜひ、千年以上続く日本の美しい習慣に思いを馳せながら、夜空を見上げてみませんか?
お月見の名所とイベント
京都・大覚寺「観月の夕べ」
平安時代から続く大沢池の舟遊び。平安貴族の気分で観月できます。
奈良・唐招提寺「観月讃仏会」
御影堂の庭園が特別開放され、鑑真和上とともに中秋の名月を愛でることができます。
滋賀・石山寺
紫式部が『源氏物語』を執筆する際に月を眺めた場所として有名。
秋に咲く彼岸花の歴史と文化
彼岸花は秋のお彼岸に咲くことからその名がつきました。
別名は「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」と呼ばれております。サンスクリット語に由来し、仏教経典に「天上の花」として登場します。そのため、彼岸花は仏教や死生観とも深く結びついてきました。
この赤い花が一斉に咲く姿は華やかでありながら、どこかはかなさも感じさせます。そのため古くから「死者の魂を導く花」とも言われ、墓地や寺院の周辺によく植えられてきました。
農村と彼岸花
彼岸花といえば田んぼのあぜ道にもよく咲いております。それには、球根に毒があるためとされております。モグラやネズミを避け、稲を守る。まさに日本人の知恵だったのでございます。つまり、彼岸花は「信仰」と「暮らし」の両方に根ざした日本らしい花なのです。
彼岸花の名所
埼玉・巾着田曼珠沙華公園
500万本が咲き誇る圧巻の景色。川の流れと赤い花のコントラストは必見です。
奈良・明日香村
古代遺跡や棚田を背景に、彼岸花が咲き誇る光景はまさに日本の原風景。
佐賀・川古の大楠周辺
樹齢3000年の大楠と彼岸花の組み合わせは神秘的。
9月は夏と秋が重なる季節。昼間は一面の彼岸花を眺め、夜は澄んだ空に浮かぶ名月を楽しむ。そんな旅は、日本の美意識を体感できる贅沢な時間です。
さらに温泉を組み合わせれば最高。例えば、奈良や京都の温泉宿に泊まって観月会に参加する、埼玉の彼岸花を楽しんだあと秩父の温泉に浸かるなど、プランを工夫すれば一層思い出深い旅になります。