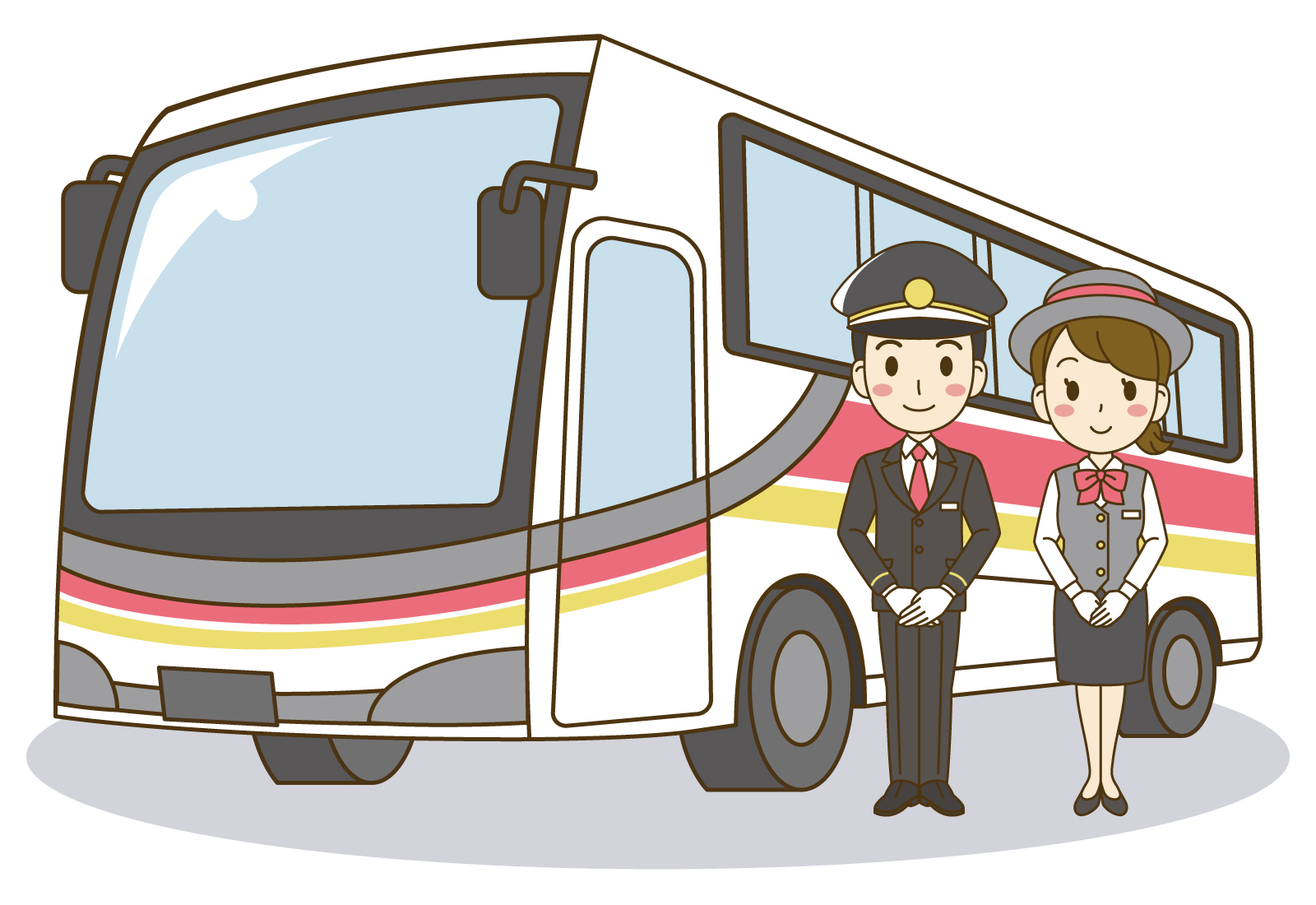観光バスとバスガイドの歴史〜日本の観光文化〜

こんばんは!Runa旅です。
観光バスといえばバスガイド。双方は切っても切り離せない、ともに日本の観光文化を支えてきました。今回は、その歴史を振り返りながら、バスガイドが果たしてきた役割をお話ししてまいります。
バスガイドの誕生と観光バス
観光バスの歴史は、大正時代から昭和初期に遡りましょう。この頃は鉄道が発達し、都市間の移動が便利にななってまいりました。その一方で鉄道ではアクセスが難しい観光地を巡る手段として観光バスが登場しました。
1925年12月15日。この日日本で初めての観光バスが東京で運行を開始しました。東京周辺を巡る添乗員同行のバスツアー始まりました。
そして1928年に大分県の亀の井自動車(現・亀の井バス)が地獄めぐりや耶馬溪巡りに観光地の案内をする女性車掌を同行させました。観光地の魅力を伝えるために「バスガイド」という職業が誕生したのです。当時のバスガイドは五・七調での案内をしていたと言われております。
バスガイドの黄金時代
戦後の復興が進んだ1950年代から70年代にかけて、日本は高度経済成長期を迎えます。この時代、修学旅行や団体旅行の需要が増加いたしました。この流れに乗り観光バスは旅行の定番と位置することになります。
バスガイドは観光案内のほか、バス内でのレクリエーションを通じて旅の楽しさを演出する役割を担うようになりました。歌やクイズ、楽しいお話しで観光客を楽しませ、明るい笑顔と丁寧な接客が「旅の思い出」の一部となりました。この頃から観光バスといえばバスガイドという認識がお客様に認識されるようになったのではと言われております。
観光バスの多様化
1980年代から1990年代のバブル経済期に入りますと、観光バスの利用はさらに広がりを見せました。企業の研修旅行や慰安旅行、地域イベントでも観光バスの利用が行われるようになりました。それに伴い、バスガイドの仕事も多様化しました。
この頃には、外国語を話せるガイドや専門知識を持つガイドが登場し始めました。今となっては英語でご案内するガイドさんも地域によって珍しくありません。しかし、この頃というのは義務教育に外国語が取り入れられるのも珍しい頃です。その為、当時はかなり貴重な存在であったと考えられています。
現代の観光とバスガイド
2000年代以降になりますと少子高齢化や個人旅行の普及により、観光バスやバスガイドの需要は減少傾向にあります。また、観光バスに関する法律改正によりバスガイドが乗務をしないバスも多くなりました。しかしその反面、訪日外国人観光客の増加により、多言語対応が可能なバスガイドが求められるようになりました。
さらに最近では、AIや自動音声ガイドの導入が進んでおります。バスガイドとしましてはなんだか複雑な心境です。
これからの役割
バスガイドの仕事の減少。高齢化。AI化と課題は山積みのバスガイド。技術の進歩が進む一方、人間ならではの「心のこもった観光案内」や「地域文化を伝える力」が再認識されつつあります。
先日のお仕事にこんな団体さんがいらっしゃいました。昨年はバスガイドを依頼せずに修学旅行を行ったという学校さん。すると先生方より「添乗員さんだけいればいいと思っていたけど違った…。単なる観光案内役ではなく、様々な話を通して各地の文化を温かく伝えてくれていたんですね」と言っていただきました。
バスガイドも人間ですので中には案内を蔑ろにする人も確かにいます。移動中DVDやゲームばかりする人も悲しいですがおります。しかし、ほんの一部の人に限られたことです。
バスガイドは、観光バスの「顔」として、日本の観光文化を支えてきました。時代とともにその役割は変化していますが、お客様に旅の楽しさや感動を届ける使命は変わりません。Runa旅は毎日全力でこれからもお客様をお迎えいたします!!
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。