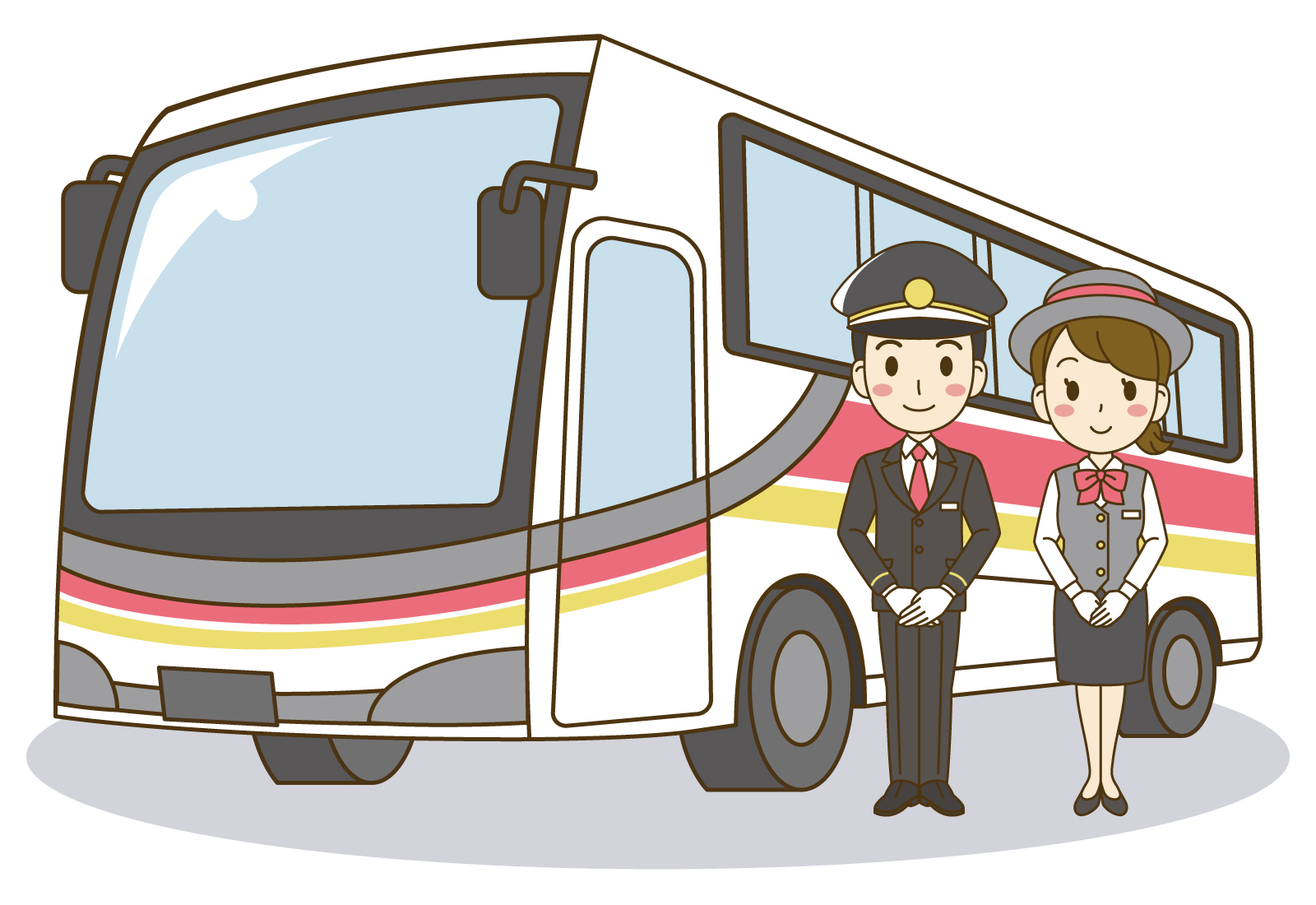【日本の夏の風習】涼と祈りを感じる旅

皆さまこんにちは!Runa旅です。
本日は日本ならではの夏の風習を紐解いて参りましょう。
暑さをしのぐ工夫や、無病息災を願う儀式、自然とともに生きる日本人の知恵が、季節ごとに表れております。
茅の輪くぐり 古代から続く厄払いの儀式
まずご案内するのは、6月30日や夏の土用入り前に行われる茅の輪くぐり。
神社の境内に現れる大きな草の輪「茅の輪」をくぐることで、半年分の厄を祓い、無病息災を祈る神事でございます。
この風習の起源は、平安時代の神事『夏越の祓』までさかのぼります。さらに物語としては、奈良時代に記された『備後国風土記』の中に登場する「蘇民将来伝説」が有名です。
旅人に宿を貸した蘇民将来公は、後に疫病から子孫を守られたとされ、茅の輪はその象徴とされました。古代から続く疫病除け・災難除けの伝統として、現代にも受け継がれております。
風鈴 魔除けと涼の音色の由来
「チリンチリン」と涼やかに鳴る風鈴には、実は深い歴史がございます。
もともとは中国の仏教寺院で使われていた「風鐸」という仏具がルーツとされております。風によって音を鳴らし、邪気を払うために屋根の四隅に吊るされておりました。
それが日本に伝わりますと、やがて庶民の間で「夏の風物詩」として親しまれるようになりました。江戸時代には、職人が江戸ガラスを使って風鈴を制作するようになりました。
涼を感じるだけでなく、音で清め、守る文化でもあったそうです。今では日本各地で陶器製のものや磁器製のもの。ガラス製など様々な風鈴が作られております。
打ち水 江戸のエコな暮らしの知恵
打ち水は、江戸時代に広まった生活の知恵と礼儀のひとつとされております。
道や玄関先に水をまくことで、ほこりを抑え、気温を下げ、そして「ようこそ」の気持ちを表す意味もございます。
当時はまだエアコンなどなかった時代。朝や夕方に水をまいて涼を呼び、お隣さんとあいさつを交わす……そんな日常の中に、人と自然、そして人と人とのつながりがございました。
近年では観光地などで「打ち水大作戦」として、再び注目を集めています!
盆踊り 鎌倉時代の念仏踊りがルーツ
盆踊りの歴史は古く、なんと鎌倉時代の踊念仏にまでさかのぼります。
そのルーツは、お盆に祖先の霊を迎えて供養する「盂蘭盆会」という仏教行事でございます。一遍上人が各地で念仏を踊りながら広めたことが起源と言われております。
江戸時代に入りますと、庶民の娯楽・地域の交流の場として定着し、歌や踊りが地域ごとに発展していきました。
現代でも、「東京音頭」や「炭坑節」、「阿波踊り」「郡上おどり」など、地域の特色を反映した盆踊りが各地で行われております。
土用の丑の日
土用の丑の日にうなぎを食べる文化、実は江戸時代の仕掛け人がいたってご存じでしょうか?
平賀源内公が、夏に売れ残って困っていたうなぎ屋に「“う”のつくものを食べると精がつく」という宣伝を考案いたしました。
それ以来、丑の日に「う」のつく食べ物を食べる風習が定着したんです。
当時、夏の暑さに対抗するために栄養価の高いものを取り入れて乗り切っていたんですね。
夏の風物詩 朝顔・金魚・花火の背景
夏といえば、朝顔市や金魚すくい、花火も外せません。
朝顔は江戸時代にブームを巻き起こし、庶民の間で交配や品評が行われるほど人気を集めたそうです。入谷の朝顔市はその名残と言われております。
金魚もまた、室町時代に中国から伝わり、江戸で「金魚売り」が現れるほど大人気になりました。
そして花火は、徳川吉宗の時代、疫病鎮魂のために隅田川で打ち上げられたのが起源とされます。庶民の楽しみとして広まり、やがて各地の夏祭りに欠かせない存在となりました。
夏の旅で、日本の心にふれる
今回ご紹介した風習のひとつひとつには、古くから受け継がれてきた歴史や想いが込められております。
ぜひ旅先で、こうした風習に出会ったら、その由来や意味に思いを馳せてみてくださいね。
夏のバス旅にあると便利な持ち物10選も合わせてお読みください。
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。