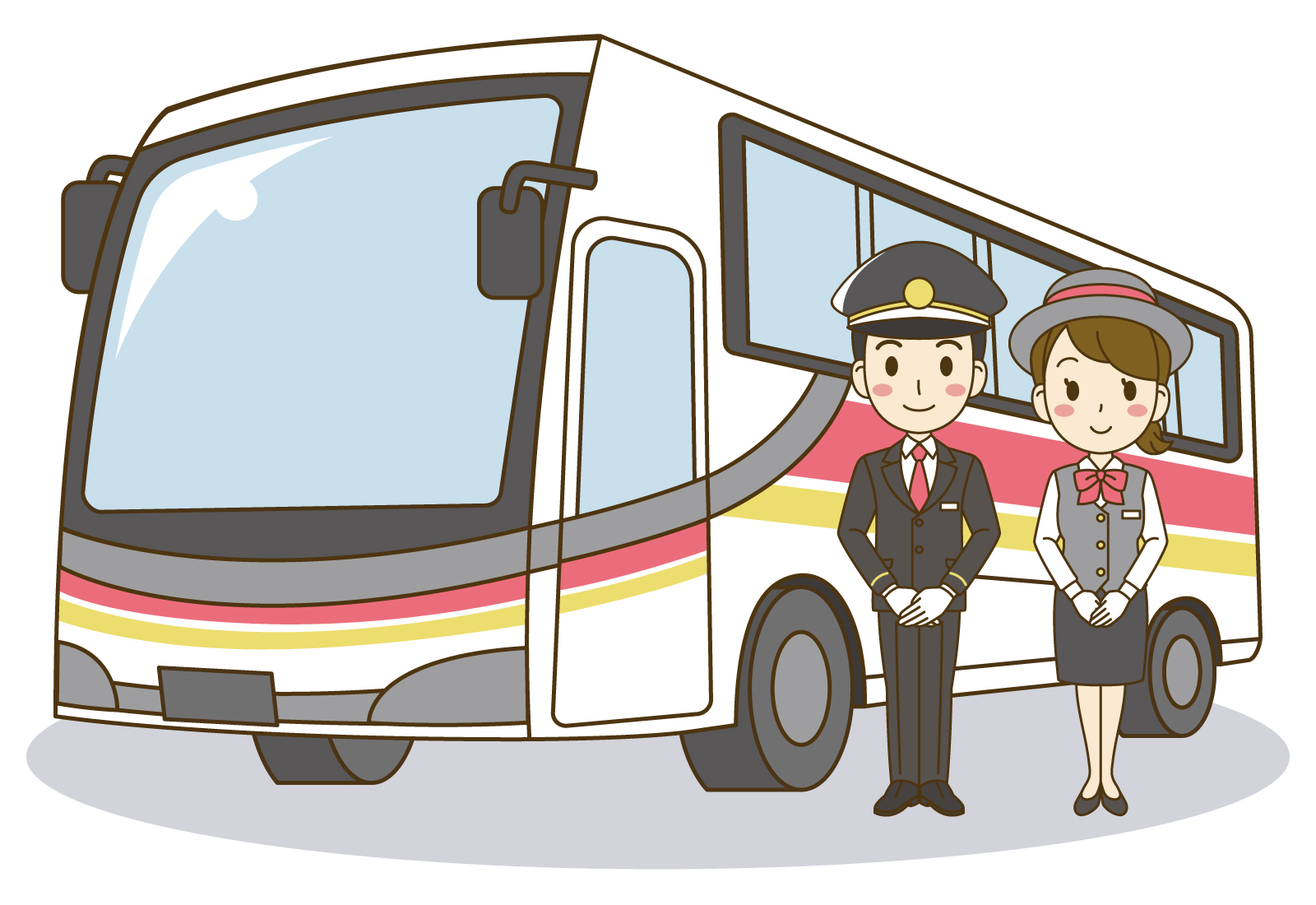【広島原爆の歴史】なぜこの街だったのか

皆さまこんにちは。Runa旅です。
8月に入り暑い日が続いております。
今では修学旅行でも平和学習として訪れることの多い広島平和記念公園。
戦争の歴史を学ぶことで、未来の平和を考えるきっかけとなれば幸いです。
昭和20年(1945年)8月6日、午前8時15分。
アメリカのB-29爆撃機「エノラ・ゲイ」より原子爆弾「リトルボーイ」が投下されました。
当時の広島は広大な軍事施設を抱える軍都でした。そして、約35万人の人々が生活する街でもありました。
地上およそ600メートルで爆発したこの爆弾は、半径2km以内を壊滅させました。その結果、広島市街地はほぼ一瞬で火の海となりました。
>爆風、熱線、放射線という三重の被害により、1945年末までに約14万人が命を落としたといわれております。
なぜ広島が選ばれたのか?
原爆投下を行う際、様々な条件から「標的の第一候補」に決定されました。
選定の際の条件としてはまず、第2総軍司令部をはじめ、軍事施設が集中していたことが挙げられております。そして、市街地が密集し、爆撃効果が「実験的」に測りやすい構造だったこと。また、事前の空襲被害が少なく、原爆の影響を明確に観察できるとされたことと言われております。
つまり、広島は戦略的だけでなく、「原爆の威力を検証する実験地」として選ばれた面もあったとされております。
被爆の実態と影響
爆心地では、約3,000度を超える高温の熱線により、人々の身体は影も残さず焼け落ちました。
コンクリート建築以外の建物はほぼ倒壊し、倒壊後には火災が発生。街全体が火の海になり沢山の方が命を落とされました。また、強い放射線を浴びたことにより数日〜数週間の間に命を落とされる方…。そして、現在も広島原爆の後遺症に苦しみながら生きる方もいらっしゃいます。
原爆ドームとその保存運動
大正4年(1915年)に広島県の物産展示・販売を行う広島県物産陳列館として建設されました。その後、昭和8年(1933年)には広島県産業奨励館に改称されております。設計者はチェコの建築家ヤン・レツル氏でございます。
昭和20年(1945年)8月6日午前8時15分。人類史上最初の原子爆弾が炸裂したのは広島県産業奨励館から南東約160m、高度約600mのところでした。
奇跡的に倒壊は免れ、広島原爆の脅威を今に記しております。
戦後には「取り壊すべき」という声も上がりました。しかし、市民の間で「平和の象徴として残そう」という保存運動が高まりました。
>>その結果、1996年にはユネスコの世界遺産に登録され、現在に原爆の脅威と平和の大切さを伝えております。
広島原爆からの復興と平和都市宣言
広島原爆により焼け野が原となった街の復興は、1949年「平和記念都市建設法」の制定により本格化いたしました。これにより国の支援を受けながら、街の再建とともに、「平和を世界に訴える都市」としての歩みが始まったのです。1955年には「広島平和記念資料館」が開館し、1964年には「平和の灯」が設置されました。
毎年8月6日には「平和記念式典」が開催され、広島市長による「平和宣言」は世界に向けて発信されております。
広島原爆から学び、未来を選ぶ旅
皆さま、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。
広島という地で学ぶ歴史は、決して“過去の出来事”ではありません。
それは、今を生きる私たちへの問いかけであり、忘れてはならない事実でございます。
長崎原爆については“長崎原爆の歴史と平和への祈り”もご一緒にご覧ください。