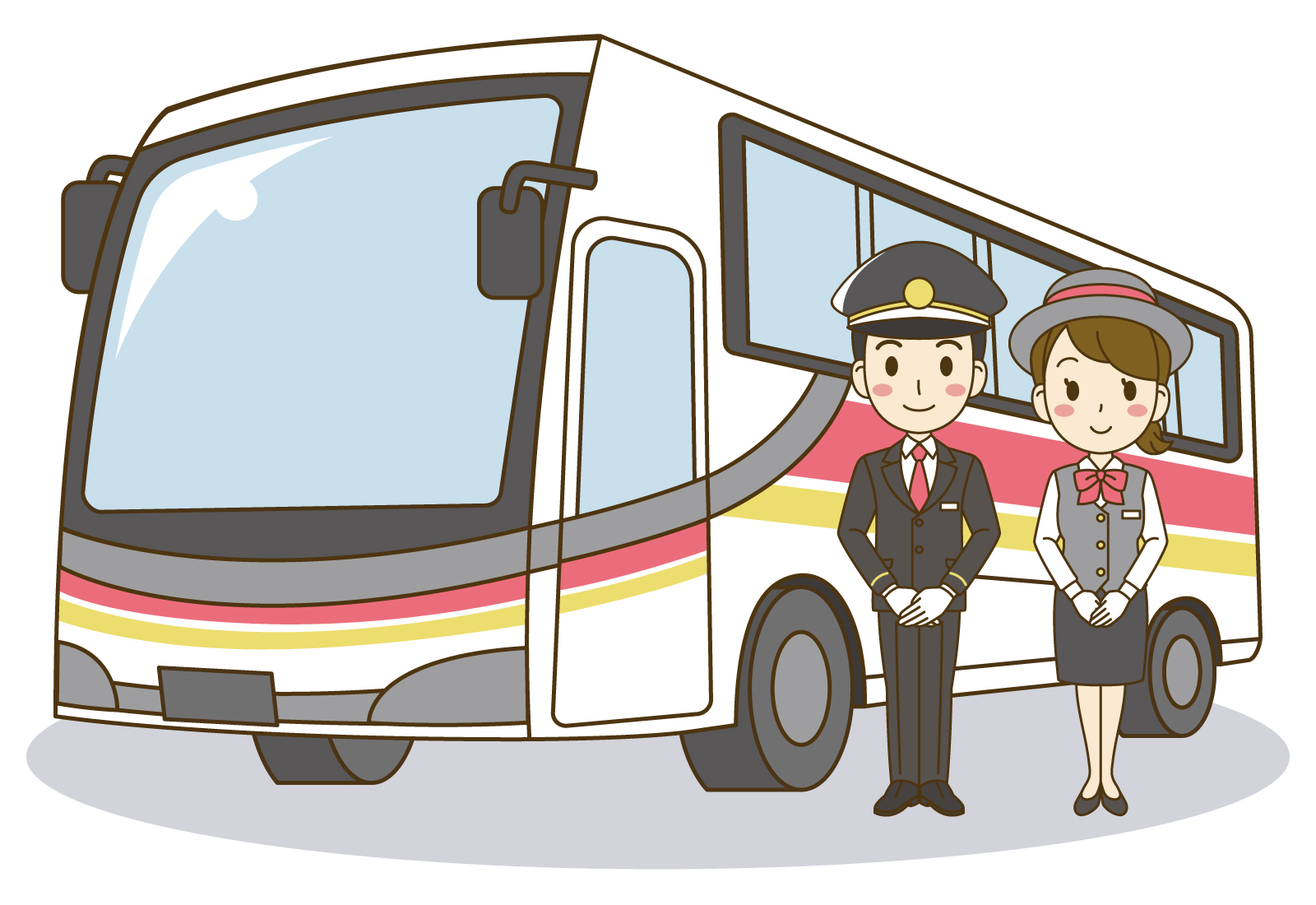日本三名泉めぐり〜有馬・草津・下呂 時を超える癒しの湯〜

こんにちは、Runa旅です。
全国には数えきれないほどの温泉がありますが、“日本三名泉”と呼ばれる湯をご存じでしょうか?
それは、有馬温泉(兵庫県)・草津温泉(群馬県)・下呂温泉(岐阜県)の三つ。
この呼び名の由来は江戸時代、儒学者・林羅山が著した書物に登場いたします。
羅山はそれぞれの湯の歴史・効能・文化を高く評価し、“天下三名泉”と称えたことから、この呼び名が広まりました。
では、今も人々を惹きつける三名泉の魅力を、歴史の息づかいとともにたどってみましょう。
有馬温泉(兵庫県)〜神々が見つけた日本最古の湯〜
有馬温泉は、日本最古の温泉として『日本書紀』にも登場いたします。
神代の昔、大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)がこの地を訪れ、病を癒したという伝説が残ります。
つまり、神様が最初の入浴客なのです!
また、奈良時代には僧・行基が湯を整備し、戦国の世には豊臣秀吉公がこよなく愛したことで全国に名が知れ渡りました。
その上、秀吉公はこの地に数度滞在し、滞在の際には毎度、湯殿を設けたことでも知られております。
現在も「太閤の湯殿館」で、その歴史を垣間見ることができます。
そんな有馬温泉の泉質は鉄分と塩分を多く含む金泉と、炭酸を多く含む透明な銀泉の二種類がございます。
まず、金泉は冷え性や筋肉痛に、銀泉は疲労回復や美肌効果に優れているといわれております。
六甲山に囲まれた温泉街は、紅葉や冬景色と相まってまるで時代絵巻のよう。
石畳を歩けば、太閤秀吉の足音が聞こえてきそうです。
📍アクセス:神戸電鉄「有馬温泉駅」下車すぐ
💧泉質:含鉄ナトリウム塩化物泉・炭酸泉
♨️効能:冷え性、疲労回復、神経痛
草津温泉(群馬県)〜“恋の病以外は治す”天下の名湯〜
「草津よいとこ 一度はおいで~♪」
この歌で知られる草津温泉は、古くから“天下の名湯”と称えられてまいりました。
起源は鎌倉時代ともいわれ、源頼朝がこの地を訪れた際に発見されたという伝説も残ります。
また、江戸時代には湯治場として庶民の憧れの地となり、徳川将軍家にも薬湯として献上されたほどです。
草津の象徴といえば、湯畑。
中心地に湯煙が立ちこめ、湧き出る源泉が木の樋を流れ落ちる姿はまさに草津の心臓。
また、湯温を下げるために行われる“湯もみ”も江戸から伝わる伝統文化で、現在も観光名物として受け継がれています。
草津の湯は強酸性。
「恋の病以外は治す」といわれるほど効能が高く、殺菌・美肌効果に優れています。
📍アクセス:JR長野原草津口駅からバス約25分
💧泉質:酸性硫黄泉
♨️効能:皮膚病、神経痛、疲労回復
下呂温泉(岐阜県)〜白鷺が導いた飛騨の名湯〜
最後にご紹介するのは飛騨川のほとりに湧く下呂温泉。平安末期から鎌倉時代にかけて知られるようになりました。
伝説によれば、一度枯れてしまった源泉を白鷺が見つけたといわれ、“白鷺の湯”として人々に親しまれてきました。
江戸時代には湯治場として繁栄し、旅籠や茶屋が立ち並ぶ宿場町として発展いたしました。
儒学者・林羅山が「有馬・草津・下呂」を日本三名泉と称えたのもこの時代のことです。
泉質は無色透明のアルカリ性単純泉。
肌ざわりがとてもなめらかで、“美人の湯”として人気です。
飛騨川沿いに点在する露天風呂や足湯は、紅葉や雪見風呂にも最適。
地元の名物「朴葉味噌」や「飛騨牛」も旅の楽しみのひとつです。
📍アクセス:JR高山本線「下呂駅」から徒歩約5分
💧泉質:アルカリ性単純温泉
♨️効能:美肌、神経痛、疲労回復
日本三名泉は、単なる観光地ではなく、「湯治」という文化そのものを今に伝える場所です。
神代の昔から、武将や文人、そして旅人たちが湯に癒やされ、そのぬくもりが脈々と受け継がれてきました。
また、どの湯も、歴史と自然が調和し、訪れる人の心をやさしく包み込んでくれます。
今度の休日には、少し足をのばし時代を越える日本三名泉へ出かけてみませんか?