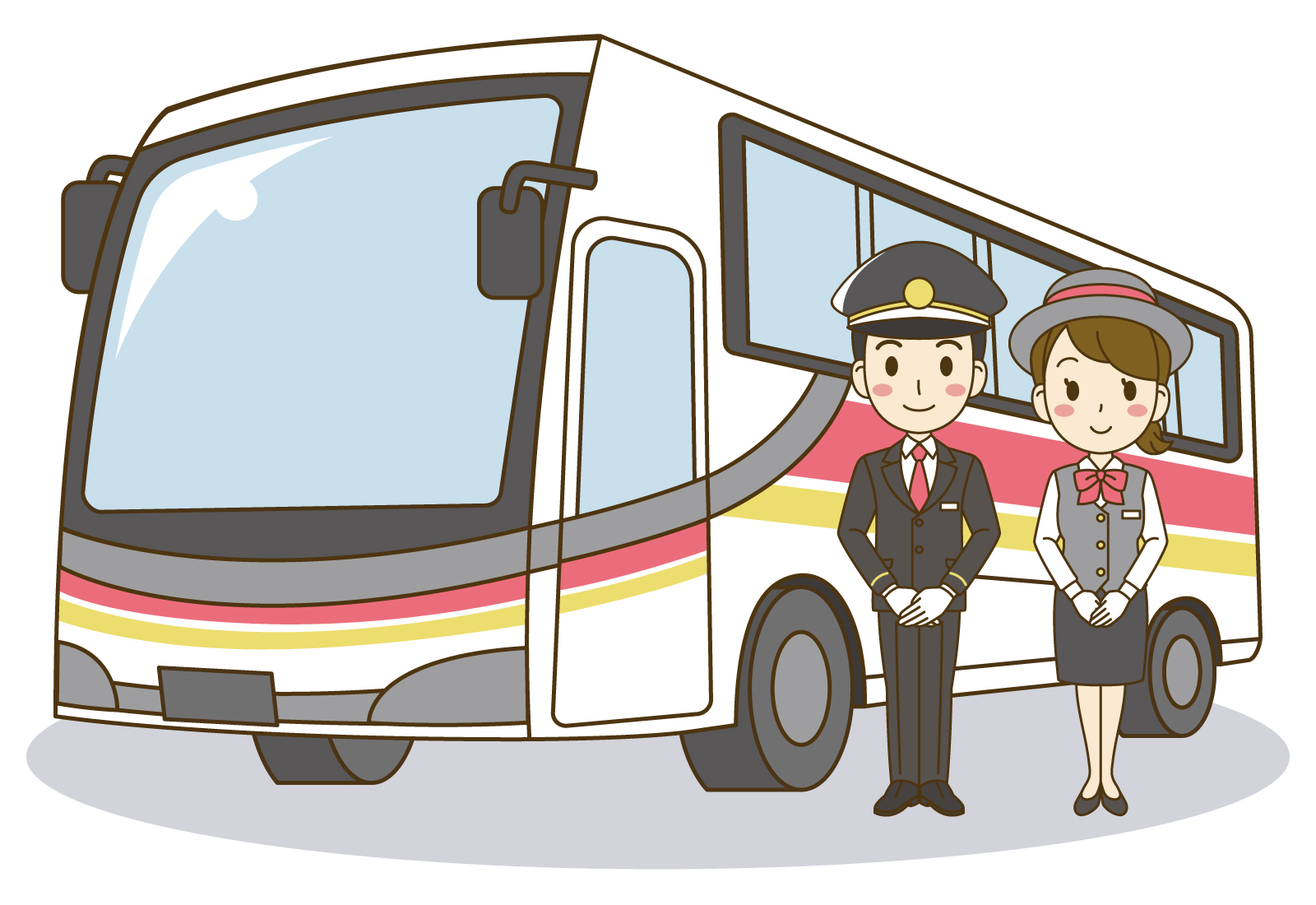秋を味わう新そばの旅〜日本各地のそばと歴史

皆さま、こんにちは!Runa旅です。
秋といえば“新そば”の季節ですね。収穫したてのそば粉で打ったお蕎麦は、香り高く、口いっぱいに広がる風味が格別です。
今日はそんな日本各地のそば文化や歴史、そしてちょっと変わったご当地そばをご紹介いたします。
そばの歴史と新そばの魅力
そばは奈良時代に中国から伝わったと言われております。当初はそば粉を練って“そばがき”として食べられておりました。
その後、江戸時代には“そば切り”が普及し、町人文化とともに発展いたしました。その中でも屋台の“二八そば”は庶民のファストフードであり、健康を支える食べ物でもありました。
また、秋に収穫される“新そば”は特に香り高くより風味を味わうことができます。“初物を食べると寿命が75日延びる”と縁起を担ぐ習慣もございました。
江戸時代のそばと健康
それでは江戸の町でそばが広まった背景を見てみましょう。
精米した白米を主食とする江戸では、ビタミンB1不足で「脚気(かっけ)」が大流行いたしました。そんな時、“脚気にはそばを食え”と言われたほどです。
そばに含まれる「ルチン」は血管を丈夫にする作用があるとされております。そして、庶民にとってそばは安くて早く大変手軽な食べ物として親しまれておりました。その上、健康にも良い食べ物として知られ、江戸の町に数千軒のそば屋が並んだのも納得のお話ですね。
全国の名物そば
戸隠そば(長野)
修験の地・戸隠山で育まれた伝統のお蕎麦といえば戸隠そばでございます。ざるに小分けした“ぼっち盛り”が特徴でございます。
出雲そば(島根)
そばを“割子”に盛り、薬味やだしをかけていただく独特のスタイルを確立したのが出雲そばでございます。松江藩の文化が育んだ一品でございます。
わんこそば(岩手・花巻)
江戸時代のもてなしから始まったとされておりますのがわんこそばでございます。次々に注がれるそばを楽しむ体験型グルメでございます。
信州そば(長野)
冷涼な気候と清らかな水に育まれた信州そば。街道沿いの旅人のエネルギー源として親しまれておりました。
更科そば(東京)
そばの実の芯だけを使った白く繊細なそば。江戸の粋を象徴する味わいでございます。
九州のそば文化
阿蘇そば(熊本)
南阿蘇一帯は冷涼な気候のもとそば栽培が盛んでございます。火山灰の土壌で育ったそばは香り高く、地元の山菜や川魚と合わせた素朴な味わいが特徴でございます。
椎葉そば(宮崎・椎葉村)
世界農業遺産にも認定された椎葉村。山深い地域で、保存のきくそばは古くから貴重な主食でございました。そばがきやそば雑炊としても食べられております。
玖珠そば(大分)
メーサーの山々に囲まれた玖珠町はそばの名所としても知られております。江戸時代から栽培されており、澄んだ水で打ったそばは上品な味。秋には新そばまつりも開かれております。
九州のそばは「山の恵み」とともにいただく郷土料理として発展してまいりました。信州や江戸の粋なそばとはまた違った、素朴で力強い魅力が特徴でございます。
ちょっと変わったご当地そば
へぎそば(新潟):海藻「ふのり」をつなぎに使い、強いコシが特徴。
高遠そば(長野・伊那):辛味大根のおろし汁でいただく爽やかなそば。
冷やしたぬきそば(北海道):天かすを豪快にのせた夏の定番。
茶そば(京都・宇治):抹茶を練り込んだ雅なそば。
そばは奈良から江戸を経て現代へと伝わり、各地で独自の文化を育んでまいりました。
江戸では健康食として庶民の暮らしを支え、九州では山間の生活に根ざした郷土料理に。
そして、秋は香り高い「新そば」の季節。全国の名物そばを食べ歩きながら、その土地の歴史や文化に触れる旅をしてみませんか?
最後までご覧いただきありがとうございました。